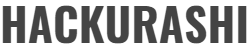従業員を抑圧する人間にならない為に必要な事
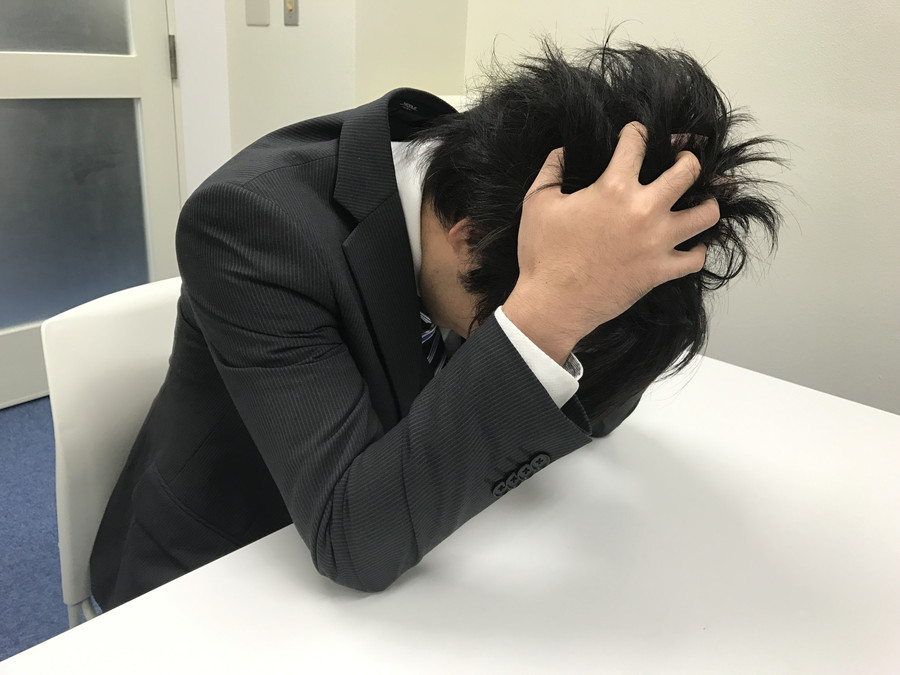
「いい上司になろうとする」という勘違い
いつの時代も問題になるのが上司と部下との関係です。
仕事をしていくときには必ず命令を出す側と、それに従い必要なことを実施していく側の役割が必要になります。
ですが、本来仕事をより効率的に行うための指示をする側の上司が部下の足を引っ張ったり、不明確な指示を出してしまうということがあります。
これは何も上司になる人間が意地悪でやっているというわけでなく、本人にしてみればよかれと思ってやっていることが、結果的に良くない方向に捉えられてしまっていることが原因です。
皮肉なことに、自分自身が若手であったときにかなりの苦労を経験していたり、そこから「よい部下を育てたい」と考えている人ほど、逆に部下を抑圧する側の人間になってしまう事がよくあります。
なぜそうしたすれ違いが生じてしまうかというと、それは部下側と上司側の「いい上司」の認識が大きく異なるからです。
数十年前の年功序列が当然であった社会においては、部下は上司に従うことが当然の常識となっており、言われたことをそのまま実行をするのが最も「よい部下」とされてきました。
しかし現在では社会全体の意識が変わり、人の「顔」で仕事をするということが出来なくなってきましてた。
また、ここ最近の若手は一つ上の世代と比較してかなり学歴が高く、基本的な教養が高いことから、非効率な業務を「上司の命令だから」と無条件に従うことは好みません。
上司にしてみれば「上司の言うことに従うのが将来伸びるためのテクニック」なのに対し、若い世代は「効率的に自分なりの業務をしていきたい」という認識を持っているのです。
どちらが完全に正しいということではなく、お互いそうした考え方の違いがあるのは、あらかじめ知っておくべきことと言えます。
「意見を聞く」がいつの間にか「気にいる意見を言わせる」になっている
年配の上司と年下部下とのすれ違いがよくわかるのが、上司側の「自分は部下の意見をしっかり聞いているのに、部下はちっとも心を開いてくれない」という意見です。
そうした上司は積極的にミーティングの席をもうけたり、飲み会などで部下と一緒に過ごすことに前向きではあるのですが、部下はそうした席をむしろ嫌がる傾向にあります。
というのは結局上司の言う「話を聞く」は、「自分に気に入る意見を言うことを強制される」ことになり兼ねないからです。
難しいことですが、こうした偽善的な行動は無意識に多くの上司がやってしまっていることです。
良かれと思っていたことがむしろ嫌われる原因になってしまわないように、常に自分の行いを振り返って、抑圧的な行動をとっていないかを振り返ってみてもらいたいものです。